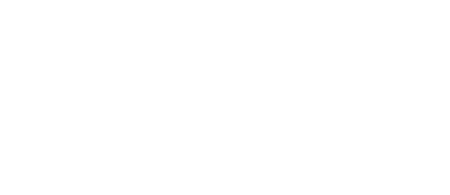まつりの由来
「しねり弁天たたき地蔵まつり」の風習は江戸時代中頃から始まったと伝えられております。
“天下の奇祭”と評判の「しねり弁天たたき地蔵まつり」が行われるのは、毎年6月30日の夜でした(今は、6月の最終土曜日)。新潟県魚沼市(旧小出町)の中心部、諏訪町にある弁天堂と陣屋通りを隔てた稲荷町の観音寺のお地蔵様との間がメイン会場となります。
一連の祭行事は、日が暮れて赤い連提燈にあかりが灯る頃から始まります。御神体の渡御や弁天踊りが各所で行われ、あちらこちらから若い男女の歓声が起こり、俄かに活気づきます。男性は女性の腕などをつねり(しねり)、女性はお返しに男性をたたくという、年に一度の無礼講が許されるお祭です。
この奇妙な祭の起源は分かっていませんが、同様の習わしや祭は各地にあります。江戸時代の川柳には「弁天のしりをつねりに巳待の夜」とあります。弁天の縁日、初巳の日は開運のお守り(巳成金)を貰うことができ大いに賑わっていたそうで、正月の初巳の夜には、若い女性の尻をつねる習わしがありました。
また、1月15日には“かゆ杖”(かゆを炊いた燃えさしの木を削って作った杖。かゆの木、お祝い棒、嫁たたきともいう)を作り、あずき粥を食べていたそうで、宝暦年間の川柳に「細腰をやなぎでたたく十五日」「かゆ杖でたたかれ嫁の腹がはれ」とあります。かゆ杖で女性の腰をたたくと“男の子が授かる”“安産になる”という、このような風習は全国的に行われており、「源氏物語」や「枕草子」にも出てきます。
「子宝祈願」「安産祈願」の「しねり弁天たたき地蔵まつり」はご利益があるユーモラスな「天下の奇祭」。御神体突入や数々の出し物が人気を呼び、年々賑わいを増しています。
【弁天堂とは】
魚沼市の弁天堂は宝永七年(1710年)の建築で、今から約300年程前に建てられました。御本尊の「弁財尊天像」は十六童子を従え、冠に鳥居と男の像を載せた華麗な容姿。極彩豊に塗り上げられた彫刻は見ものです。
この弁天堂は昔から五穀豊穣、縁結び、子育て、不老長寿、商売繁盛の神様として近郷近在に広く深い信仰を集めていました。
そして観音寺にある大きな座り地蔵は火伏地蔵で、もともと防火の為に街の出入口(小出橋のたもと)に置かれていましたが、明治初期に観音寺に移されたそうです。